eBookダウンロード|会議と会議音声のナレッジベース
アフターコロナを見据えたハイブリッド授業環境の構築
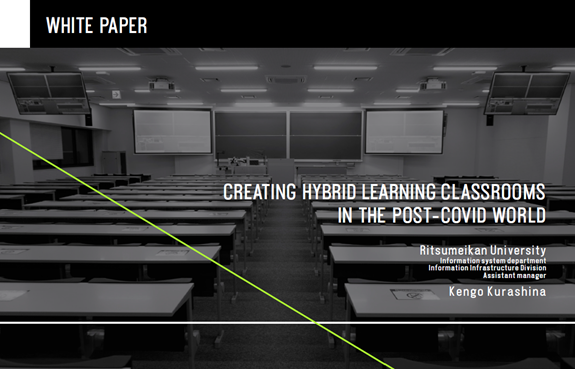
ダウンロードいただけるガイドブックについて
パンデミック以降、多くの教育機関は対面授業からオンラインを交えた授業への転換を余儀なくされ、様々な代替手段を模索しながら学びの場と機会を提供しているのが現状です。
その最優先課題のひとつが、マイクが遠く先生の声が聞き取りづらい、空調など不快な環境音(ノイズ)が同時に聞こえて疲れてしまうなど、音の問題です。また、特に対面とオンラインを併用するハイブリッド授業の場合、講義音声が明瞭であっても、離れた自宅で講義を受けている生徒は疎外感を感じやすく、「物理的に離れていても、同じ学びの空間を共有している」という臨場感を感じてもらうための工夫が求められています。
こうした課題に対して、Shureの音響ソリューションを巧みに利用しながらわずか30日間で600教室をハイブリッド授業へ対応させ、「対面授業のみだった頃よりも双方向性が高まったケースもある」とまで言わしめた立命館大学の情報基盤課 倉科氏が、自身の体験を執筆したのが本書です。
想定読者
- 大学ほか高等教育機関のIT部門、学内IT/AV設備担当部門に従事される方
- 企業でのオンライン会議システムの構築にお悩みのシステム担当者
目次
いかに学びを止めないかを考え、まずは全授業をオンラインに
大学らしさを味わえるハイブリッド授業へ
異なる既存設備を利用しながら、すべての教室で同じ環境構築を目指す
臨場感あるオンライン授業への工夫
シンプルな操作を追求、機能をUSBケーブル1本に
オンライン授業で課題だった音響問題を解決
双方向性が高まり、授業の質が向上
ビジョンの明確化とあきらめない意思
まえがき抜粋
授業はさまざまな面で多様です。大人数で受ける講義の科目から、先生と生徒のやり取りで進行する語学やゼミなど、形態は多彩で教員のITスキルもさまざま。さらに立命館大学の教室は大小合わせて600を超えており、物理環境も異なります。これらの多様なニーズに柔軟に応えることが求められる一方、オンライン環境が唯一のつながりになりますので、学びの質に大きく影響する「聞こえない」「見えない」といった状況は許されません。学生にとっても教員にとってもストレスのない、シビアなシステム構築が求められます。
本稿では、これまでの取り組みの中で蓄積した知見やノウハウに加え、わずか1か月で約600教室のオンライン環境を構築した経験や、その実践の中で得た新たな気づきを、同じく教育機関で映像音響設備やITをご担当されている皆さん、授業のオンライン化やその改善を大きな経営課題として担っている経営層の皆さんへ、ぜひ共有したいと思います。

著者
倉科健吾
立命館大学 情報システム部情報基盤課 課長補佐。立命館大学政策科学部卒業後、専門商社を経て、2004年学校法人立命館に入職。立命館では情報システム部門に在籍し、主に教室等の映像音響システムの整備を担当。立命館大学全キャンパスと立命館アジア太平洋大学の教室の映像音響システムの改修・管理を担当し、新キャンパス整備やリノベーションなど数多くのプロジェクトで情報環境の整備をマネジメントしているほか、日常的な保守を統括している。これまで10人規模から1000人規模まで、講義室やホール、アクティブラーニング教室や遠隔会議室ほか延べ約2000教室のICT環境構築・保守管理を手掛けている。
Microflex Advacne MXA902 シーリングアレイスピーカーホン
中小規模会議室向けシーリングアレイスピーカーホン「MXA902」。
高度なアレイマイクロホンと広拡散スピーカーを内蔵し、自然なスピーチ音声の収音と出力を実現。
動画|会議用スピーカーホンは、天井へ。特長を徹底解説。
中小規模会議室向けシーリングアレイスピーカーホン「MXA902」。
高度なアレイマイクロホンと広拡散スピーカーを内蔵し、自然なスピーチ音声の収音と出力を実現します。シングルゾーン・オートマチックカバレッジ™テクノロジーにより6m×6mの範囲の音声を収音し、IntelliMix® DSPがエコーやノイズのない音声を提供します。本動画では新製品MXA902の特長を解説します。